
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]

就労継続支援A型事業所において、利用者が無断で通所を中止し、連絡が取れなくなるケースは少なくありません。本記事では、こうした事例に対して事業所がとるべき具体的な対応方法を解説します。社会保険や雇用契約の観点からのリスク、就業規則・契約書での明文化のポイント、実務対応の注意点をわかりやすくまとめています。
就労継続支援A型事業所に限ったことではありませんが、利用者が無断で通所を中止し、その後まったく連絡が取れなくなってしまうケースが時折発生します。
特に、就労継続支援A型では雇用契約を結んでいるため、様々な問題が起こってきます。
例えば、社会保険に加入している利用者の場合、雇用契約上の手続きや退社処理が必要となるため、事業所としては適切な対応が求められます。
今回の記事では、このような事例に対する具体的な対応方法についてご紹介します。
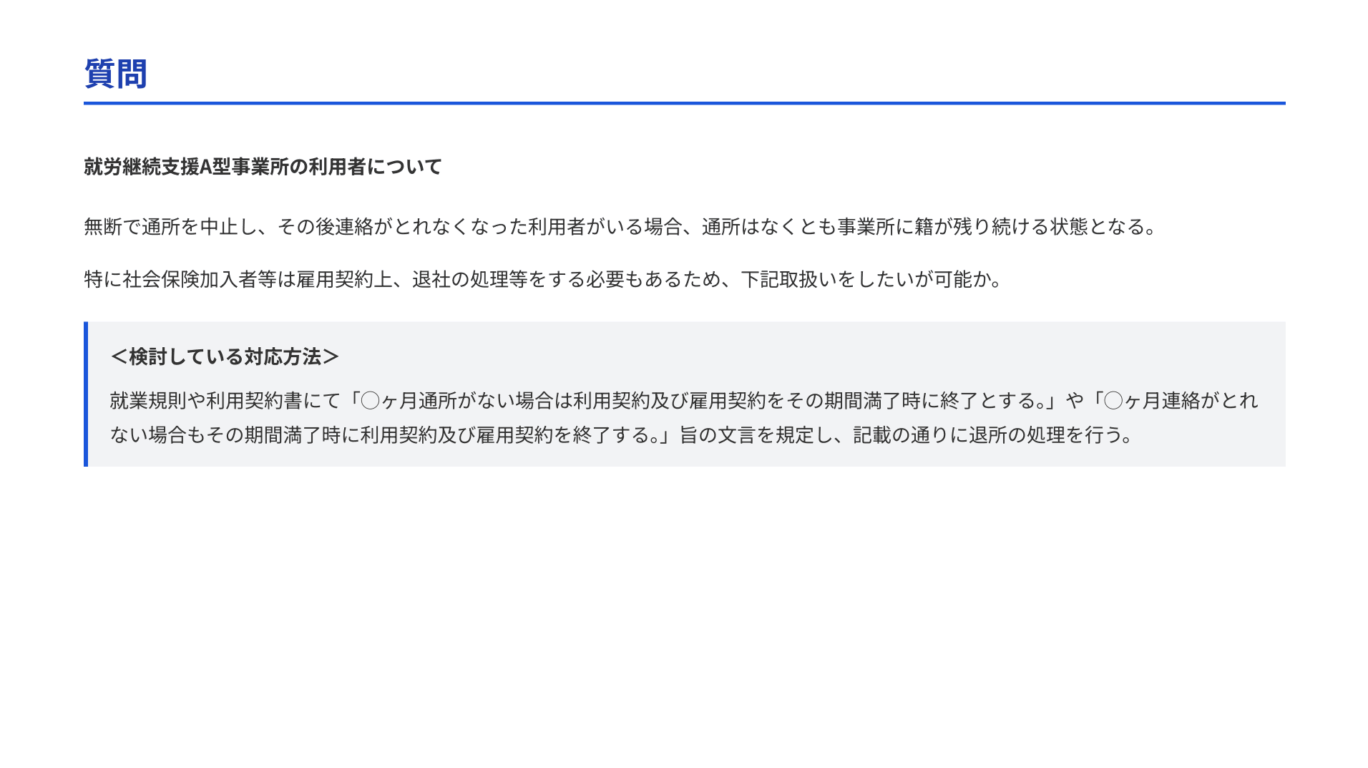
無断で通所がなく、連絡も取れなくなった利用者がいる場合、利用実態がないにもかかわらずその事業所に在籍している状態が続いてしまいます。
この状態が続くと、社会保険料の負担の問題や、実際の雇用状況と書類上の状況の乖離によるトラブルなど、事業所にとって様々なリスクが生じます。
例えば、雇用保険や社会保険の資格喪失手続きが適切に行われないと、 後になって未納分の請求や行政指導の対象となるおそれもありますので、こうしたケースには早期かつ明確な対応が必要不可欠です。
このような場合に備えて、就業規則や利用契約書の中に「一定期間通所がなかった場合」や「一定期間連絡が取れなかった場合」に、 利用契約及び雇用契約を終了する旨の規定をあらかじめ明記しておくことが有効です。
具体的には、以下のような内容を盛り込むことが考えられます。
・一定期間(例:2ヶ月)通所がなかった場合、利用契約、雇用契約をその期間満了時に自動的に終了とする
・一定期間(例:2ヶ月)連絡が取れない場合も同様に、契約終了の対象とする
このような規定を設けておけば、問題が発生した際にも契約書や規則に基づいて適切かつ円滑に退所・退職手続きを進めることができます。
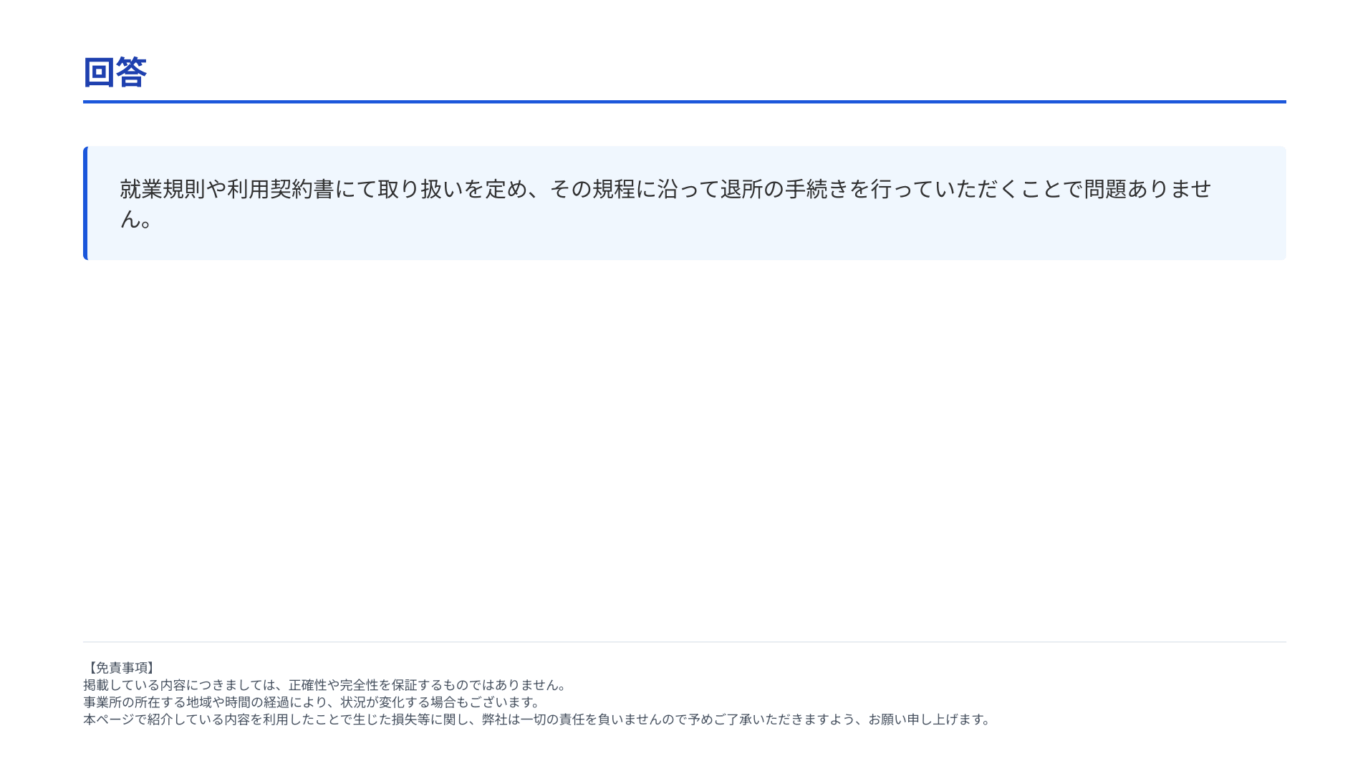
規定に基づき契約終了の手続きを行う場合、できるだけ以下の点に注意しましょう。
・契約書や就業規則の該当項目を改めて確認し、手順に沿って進める
・利用者本人への通知を可能な限り行う(郵送やメールなど、証拠が残る方法が望ましい)
・手続き内容や経緯をしっかり記録し、トラブル防止のための証拠を残しておく
・社会保険資格喪失などの事務手続きを速やかに行う
こうした対応を徹底することで、事業所側のリスクを最小限に抑えつつ、適切な運営を継続することができます。
就労継続支援A型事業所において、無断欠勤や連絡不能となった利用者への対応については事前に契約書や規則に明記しておくことで、万一の際にもスムーズかつトラブルなく対応できます。
ぜひ、今一度ご自身の事業所の規定を見直してみてはいかがでしょうか。
【免責事項】
この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。
事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。
本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
全国対応(訪問・オンライン)