
行政書士
安田 大祐
リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。
[障害者向けサービス]
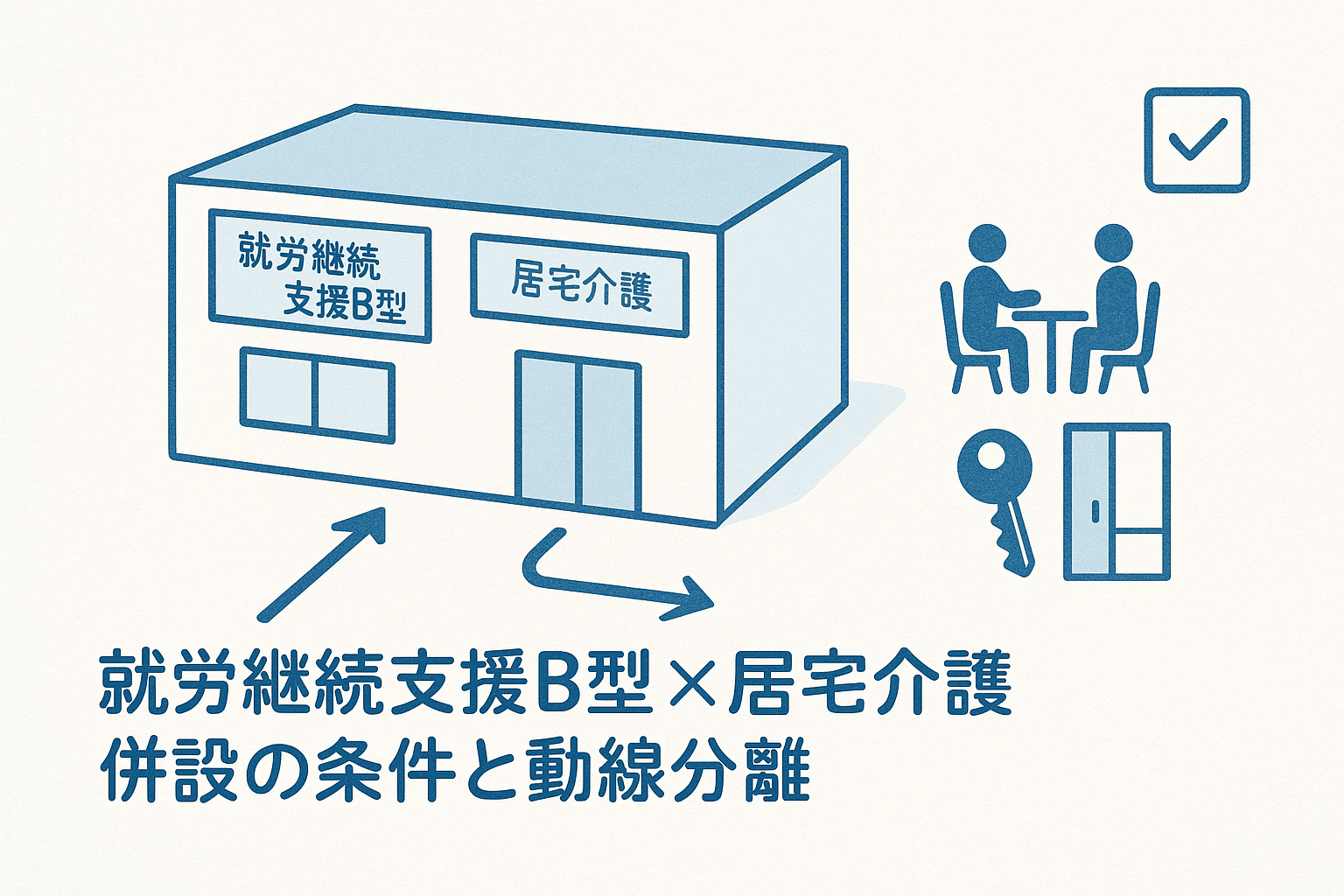
就労継続支援B型事業所と居宅介護事業所を同一建物で併設する可否や条件を解説。動線分離の必要性、自治体ごとの運用差、併設のメリット(コスト削減・連携強化)まで、開設前に押さえるべき実務ポイントをまとめます。
障害福祉サービス事業所の開設を検討する際、「複数のサービスを同じ建物で運営できないか」というご相談をいただくことがあります。
その中でも、今回は就労継続支援B型事業所と居宅介護事業所の併設について詳しく解説します。

結論としては、一定の条件のもとで併設が可能です。
就労継続支援B型事業所と居宅介護事業所を同じ建物内に開設することは可能です。
ただし、就労継続支援B型の部屋を通らないよう居宅介護事業所の受付等が配置されることが条件となっています。
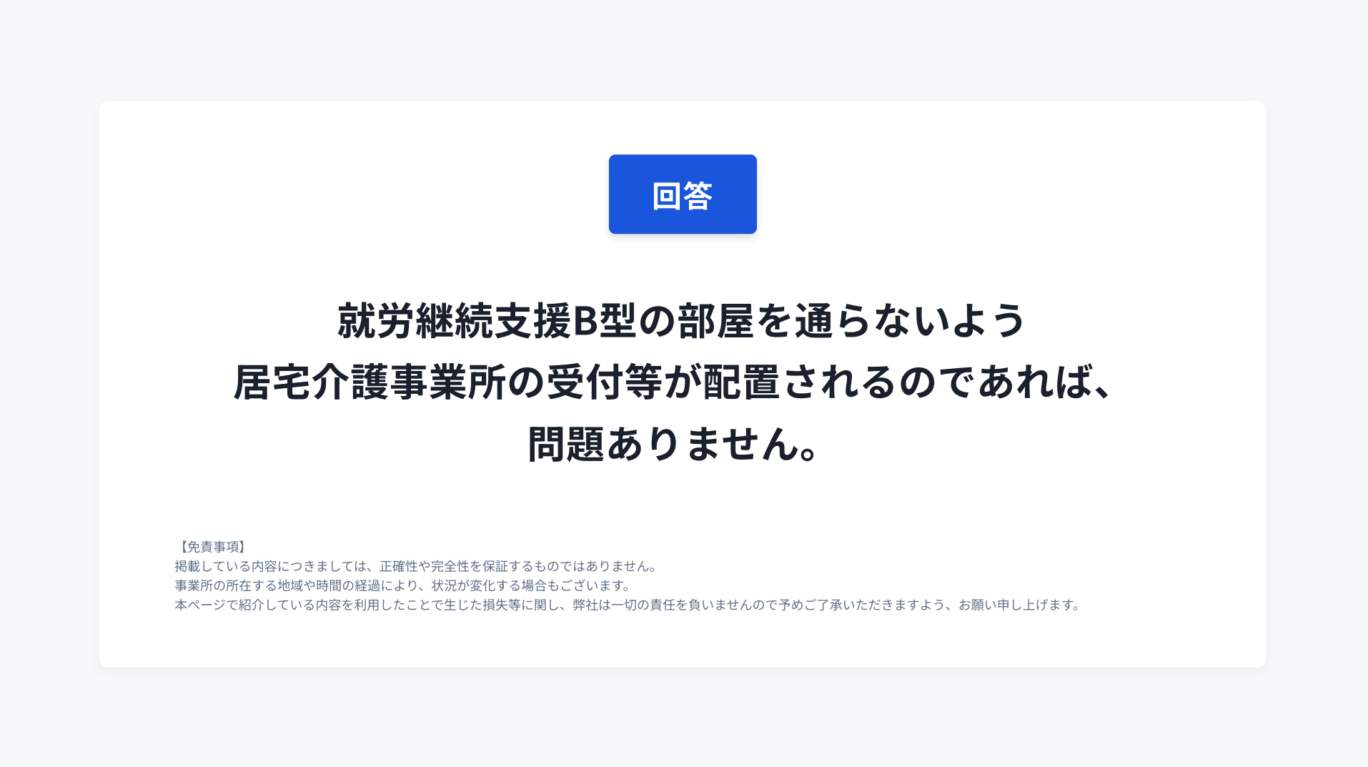
この条件が設けられている背景には、それぞれのサービスの性質が関係しています。
就労継続支援B型は、利用者の方々が訓練や作業に取り組む場所です。
居宅介護事業所は主に居宅介護員の拠点や利用者の相談の場として機能しており、職員や利用者家族の出入りがあります。
それぞれ利用者も性質も異なるサービスとなっていますので、これらの動線が交錯すると、就労継続支援B型の利用者の作業環境に影響を与えたり、居宅介護の利用者のプライバシーの確保が困難になったりする可能性があります。
そのため、就労継続支援B型と居宅介護の動線を明確に分離することが求められます。
自治体によっては、事業所への出入口もサービスごとに分けて設けなければならないとしている場合もあります。
また、サービスの組み合わせによっては多機能事業所として取り扱われる場合や、そもそも同じ場所では開設ができないという場合もありますので、個別に確認する必要があります。
制度上、いくつかのハードルがある同一建物での複数事業所の運営ですが、同一建物での運営には多くのメリットがあります。
空いている部屋を有効活用することができたり、同じ建物を使用することで他に物件を借りる必要がなくなり、1サービスあたりの家賃や光熱費などを下げられたりするなど、コスト削減の効果が見込めます。
また、同法人の職員間の連携がスムーズになることなども挙げられます。
障害福祉サービス事業所の併設を実際に検討するにあたっては、事業所所在地の自治体への事前相談が必要不可欠です。
地域によっては解釈や運用に違いがある場合もあるため、建物の図面を持参して相談するようにしましょう。
利用者の安全への配慮と快適な環境の確保を忘れず、慎重な検討を行うことが大切です。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
全国対応(訪問・オンライン)